堆肥は主に土壌改良の効果を期待して使用する資材です!
堆肥はどう使う?
堆肥といわゆる肥料の使い分けは↓が目安。
堆肥
・硬くなった土を柔らかくフワフワにする
・土の中の微生物を増やし、植物の成長を助ける
・微量要素の補充(窒素、リン、カリウムなどのメイン以外の肥料成分の補充)
一般的な肥料(化成肥料、配合肥料、無機肥料など)
・狙った特定の肥料分を効率的に補充(植物の成長に多く必要な養分)
┗窒素、リン、カリウム、マグネシウム、カルシウム、硫黄など
堆肥はいつ使う?
タイミング(時期的なこと)
基本的に野菜を植える1か月程前に土と混ぜて馴染ませておきます。
※野菜を植えて育ている最中や直前に投入すると、土の中で微生物や養分の状態が大きく変わり植物の成長に悪影響を及ぼします。
既に野菜を植えている状態で、土壌改良(土質改善)をしたい場合は、緑肥作物の混植をオススメします。
※樹や果樹など通年で植えてある植物は、冬などの成長のオフシーズンに投入すると良いケースが多いです(植えている植物ごとに調べることをオススメします)
土の状態がこんな時に
・土がカチカチな時
・水が浸み込まず、水たまりが長く残るようなとき
・砂が多く、植物を植えても根が張らず倒れてしまうとき
┗砂質を好む植物もいます
堆肥の種類
堆肥は大きく分けて、動物性の堆肥と植物性の堆肥があります。
動物性の堆肥では
土壌改良効果の大きさは以下の順です。
牛糞≒馬糞>豚分>鶏糞
※鶏糞については堆肥と言うよりは肥料的な効果がメインで使うことが多いです。
また、動物性の堆肥はその動物のフンを主原料にしていますが、製造の工程でしっかり完熟させているモノが多く、完熟した堆肥を使えばいわゆるフン的な意味での汚さは心配ないと思います。
植物性の堆肥には
バーク堆肥や腐葉土などがあり、繊維分が多く含まれているため硬く締まった土を柔らかくするのに優れています。
堆肥の使い方や効果
堆肥の使い方
基本的に、改良したい土の中に入れて土と混ぜます。そうすることで、堆肥の成分が充分に行き届き効果が高まります。
土の表面に撒くだけでも少し効果はあると思いますが、土と合わさる部分がとても少なくなってしまうので、混ぜて使うことをオススメします。
堆肥の効果
先に書いた、土をフカフカにする・微生物の増加を勉強っぽく書くと↓。になります。
堆肥で期待する土壌改良の効果は物理性(フカフカにし排水性、保肥力などが向上する)と生物学性(微生物の増加など)です!
┗ちなみに生物学性を改良することで、その後の効果で物理性の改良につながります(微生物の増加→団粒構造の増加など)
仕組み なぜ土が柔らかくなる?
堆肥を入れるとなぜ土がフカフカになり、植物の根が張りやすくなるか。
個人的なイメージは人間で言う、腸活で食物繊維をとって腸内細菌を元気にして体調改善をするような感じと思っています。
まず植物性の堆肥の説明から。
植物性の堆肥には枝の皮や葉など繊維質が多く含まれており、それらが土の中に混和されることで、微生物たちのエサや住みかとなり微生物たちが元気になります。
そうなることで、微生物たちが出す分泌物や微生物自身の活動により土が柔らかくなります。
また、それだけでなく土が肥料成分を保持する力(保肥力)や水分を適度な状態に調整する力(排水性・保水性)、空気を取り入れる状態(通気性)を持たせることができます。
動物性の堆肥はより土の中の微生物が分解しやすいので、比較的効果が出るのが速いです(あくまで植物堆肥と比べてなので、効果を感じるのに1~6カ月くらいはかかります)。
では、なぜ効果が出るのが速いのか。それはこの堆肥は動物の排泄物、つまり既に植物が動物によって分解されている状態の堆肥だからです(細かく言うとその状態からさらに微生物によって分解させています)。
そのため、何ステップか分解が進んでいるので土に入れた時に、土壌中の微生物の分解が進みやすいのです。
動物性の堆肥はそれ自身が柔らかくフワフワしているので、土壌改良について相乗的な効果が期待できます。

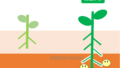
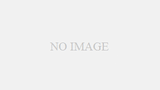
コメント